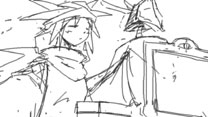|
|||||||||
|
■紙芝居王_第一集第七景
『這い上がった曰くありげな泥沼から』_ver_0.31 「ぬっ、沼の主だぁぁっ!」 悲鳴を上げ、村の子供達が逃げ出す。足がもつれ小太りの少年が転んだ。震える足で立ち上がり、彼は泣きながらまた駆け出す。遅れた少年が気になったお下げの少女が沼を振り返る。泣き叫び草むらを駆けてくる少年の向こうで、暗い沼の縁から飛沫を上げ、茶色い塊が飛び出した。膝丈ほどの草むらに降り立ち、ゆらりと躰を起こしたその泥の化け物が、ヘドロしたたり落ちる両腕を広げ叫んだ。 「こるぁああ! またんかい!」 少女が甲高い悲鳴を上げた。足が竦む彼女を、必死の形相の少年が追い越した。少女も二度と振り向くことなく駆け出した。 「……ったく。泥まみれで困ってる旅人見て逃げ出すやなんて、あのガキ共、どーいう躾されとんねん」 悪態をつきながら、ユトが袖で顔を拭った。曇り空の下、小さな人影達が草原を遠ざかっていく。ねっとりとした不快感に、旅の活弁士は身震いした。袖も泥まみれだったことに、彼女はようやく気づいた。 背後の暗い沼で一つの波紋が広がり、黒く丸い塊が浮かび上がった。凝縮された霧のようなそれは、音もなく水面を漂いながら黒い靄となり、やがて風に揺れる黒衣へと姿を変えた。岸に近づく黒衣の上部に白い胸当てが生まれ、その甲冑の中から仮面の頭が現れた。沼の縁までやって来た白仮面は、静かに草むらへ足を降ろした。 「あ! あんた全然汚れてへんやん。なんでやねん」 相棒に向かい、ユトが非難の声をあげた。人ならぬ繰人(くりと)であるバムザは、黒衣から左腕を一本突き出した。左手には一枚の横長の紙が掴まれていて、そこには長耳古語の一文が認めてあった。 『もう少し待ってから出れば良かったのに』 「なんや。ドロまみれになったんは、うちのせいっちゅーんか!? 大体、こんなとこ放り出されるくらいやったら、あの中洲から泳いだ方が良かったやん」 『……』 バムザは二本目の左腕を突き出して答えた。不機嫌な相棒は、早速くってかかった。 「『点々々点々々』ってなんやねん! んなこと、その仏頂面見たら猿でもわかるわいっ」 『それより後ろ』 「後ろ?」 三本目の左腕を突き出した大柄な黒衣から、ユトが泥滴る髪を揺らせ顔を覗かせた。二人が出てきた背後の沼の中央に、奇妙な泡立ちが生まれていた。それは見る見るうちに大きく音を立ててはじけ始めた。岸辺が微かに震え出し、沼の水面に次々とさざ波が現れた。ユトが顔をしかめて言った。 「勿体ぶった前振りやな。なぁ、バム。なんか出てきたいみたいやけど、どないする?」 『……』 「『点々々点々々』ってあんた、さっきの紙で横着しなや。それよか、あーゆーの。無視したら後々根に持たれるんちゃうかな。もーちょい見とく?」 さざ波の中心が派手に泡立ち始めていた。ユトが斜め上を見上げる。バムザは沼の縁から少し離れ振り返った。成り行きを見守るつもりらしい。泥まみれの小娘がにんまり笑った。 「やっぱそっか。でもヤバい奴やったら、すぐ逃げよーな」 二人の旅人が見守る中、沼の泡立ちは勢いよく水飛沫を上げて弾けた。大きな地鳴りと共に沼から姿を見せたのは、小山のように盛り上がった泥の塊であった。塊の両側に、長い爪を持つ腕のようなものも続いて現れた。絡みつく水草や水苔、突き立つ枯れ枝などをまとわりつかせたそれは、沼の周囲に更なる異臭を放ち始めた。ヘドロを滴らせた泥山の側面に、二つの黒い穴が生まれた。それらは岸に立つ旅人を捉え瞬きした。そして目と思しきそれらの下にもう一つ、大きな黒い穴が広がるや、大地を揺るがすかのような轟音が響き渡った。 「儂の眠りを妨げる奴は、誰だぁぁぁっ!!」 ユトが吹き出した。 「ベタやっ! めちゃめちゃベタやんっ!! ちょっとあんたっ! せっかく出てくるん待ったったんや。もーちょい気の利いた挨拶できんか!?」 「……」 『……』 腹を抱えて笑う相方の肩を叩き、バムザが魔物の沈黙を伝えた。 「だからそれはもーえーっちゅーねん。あぁーあ。わざわざ待って損したわ。ほらバムッ、もー行くで」 予期せぬ相手の態度に虚を突かれた魔物は、きびすを返した二人の背に向かい、再び大声を張り上げた。 「聖地に踏み入った挙げ句、この沼の主の微睡みを破るという愚行を重ねし者達よ。よもやこのまま立ち去ることが叶うなどとは思うまい!」 旅人達は遠ざかりつつあった。一つ息を吸い込むと、沼の主は三度、声を張り上げた。辺りを震わす怒声には、心なしか切実な響きも混じっていた。 「無礼にも背を向け立ち去るというのかっ! ならばこの咎。近隣の村の者共を喰らうことでしか贖えぬなっ!」 旅人達の足が止まった。振り返った小娘が、射竦めるような視線で冷ややかに言った。 「あんたそれ、八つ当たりっちゅーねん。沼の主かなんか知らんけど、構ってもらえんから村人襲おうなんて、知恵の足りん奴のやることやで。捻りのない台詞共々、ほんま頭悪いやっちゃな」 「儂を見て恐れぬばかりか、暴言を吐き続ける愚か者共よ。まずはお前達から喰うてやろうか」 「さっきから聞いてりゃ、喰う喰ううるさいわ。喰うなんてのは生きる為にするこっちゃ。腹立ち紛れにすることやあらへん。脳味噌まで泥詰まって、そんなこともわからんか、このド阿呆!」 バムザが沼の縁まで巨体を伸ばした主に向けて、紙を差し出していた。それに気づいたユトが覗き込む。 「なになに……『説教臭いこと言ってますが彼女、子供に逃げられた上、泥まみれで機嫌が悪いだけなんです。こちらこそただの八つ当たりなので、どうぞお気を悪くなさらないで下さい。眠りを妨げすみませんでした』……ってアンタ、あんなバケモンの肩持ってどないすんねんっ」 草むらに片爪をかけた主が少し動きを止め、ゆっくりと尋ねた。 「……その者は、この沼の主に何かを伝えようとしておるのか?」 バムザの文字が読めなかったらしい。悪戯好きな笑みを浮かべ、ユトが沼の主に明るい声で言った。 「こいつもこー言うとるんや。『可憐な彼女の言う通り。お前のような無様な能なしは初めてだ。とっとと沼底に沈んで、二度と浮かび上がって来るな! くたばれっ!!』やって。正直な奴やで」 バムザは猛烈に首を振った。沼の主は怒り狂い、その巨体を持ち上げた。小高い丘が更に盛り上がり、地平一面を覆うかのような泥山が沼の上に盛り上がった。ヘドロを滴らせて身体を伸ばした沼の主は、灰色の空を背に、ユトとバムザに覆い被さるかのように見下ろした。そんな相手を不敵に見上げ、ユトが言った。 「おっ! さっそくうちらを喰うて、自分の馬鹿さ加減を誤魔化す気やな。これやから世の中の能なし共は進歩せんのやなー。とりあえず、こんなとこまで泥落としに来んな! 余計泥まみれになるやん」 「もはや逃げられまいぞ。この沼の主を怒らせたこと、腹の中でとくと後悔するがいいっ」 今にも襲いかかろうとする沼の主。わざとらしく視線を横に逸らせたユトが、ターバンからゆらゆら飛び出した髪を弄りながら言った。 「大体、一目見てわからんかなー。うちらなんか喰うてもうまないでっ。この黒いのは肉っけないし、杜人(もりびと)なんか丸飲みしても食あたりや」 「今更命乞いか。小者共のしそうなことだ。だがもう遅い。口も悪ければ味もマズそうなお前達だが、村を襲う前の前菜にはなるだろう。覚悟せいっ!」 「あー、覚悟ねぇ。別にしてもええけど。ところでうちら芸人やねん。喰われる前に、一芝居打ちたいなー」 「芝居だと? そんな物で逃がれることなどできまいぞ」 「逃げへん逃げへん。心残りなだけや。馬鹿なあんたにもわかりやすい話にしたるで。こんなへんぴな沼の底に沈んでて、おもろいこと、なーんもあらへんやろ? うちらも芝居見てくれた奴に喰われるんなら、そんなに腹も立たんかもしれんし」 沼の主が僅かに身を引き、問いかけるように言った。 「腕に覚えでもあるような物言いだな」 「当然。さっきからうるさいあんたを黙らせるくらいのことはできるやろなー」 それまでの気のない物言いから少し得意げに話し始めたユト。強者の余裕を見せねばと思ったのだろうか、沼の主は小娘の言葉に乗せられるように言葉を返していた。 「よかろう。ならばその芝居とやら、やってみるがいい。なかなかの見物ならその命、見逃してやらぬでももない。しかしもしそれが取るに足らないものならば……その時は観念するがいい」 ユトが合点したというように一つ手を打って笑った。 「あぁ、そーいう話か。えーで、やったるわい。でももし芝居見た後で、うちら喰う気なくなってたら……その時はあんたこそ、覚悟しぃや。こっちの言うこときいてもらうで」 「よかろう。その威勢がいつまで続くか、見てやろうぞ」 「威勢より、芝居の方、ちゃんと見ときや」 バムザは既に準備を終えていた。絵師は最後に、黒衣から出した講釈台をユトの前に置き、自らは沼に向けられた額縁の裏側に回った。ユトは静かに目を閉じた。沼の辺から大気に向かって耳を澄まし、彼女は語るべき言霊を集め始める。泥まみれの格好とはうらはらの真剣さが、転瞬、張りつめた空気となって辺りに伝わった。懐から汚れを免れた扇子を取り出すと、ユトは景気よく講釈台を一打ち、瞼を開く。榛色(はしばみいろ)の瞳を輝かせ、活弁士は語り始めた。 「ここに語るは『夕霧海王転生譚』……って、……わかるか? 威張って牙を剥きだしするしかできん能なしのあんたにもわかるように、題名かみ砕いたるわ。つまり、夕霧海王とか名乗って威張ってる南の霧の海の魔物が、空前絶後の食あたりを起こす物語や」 「くだらない戯れ言だろう。儂はそんな脅しにはのらんぞ」 「脅しかどうかは芝居を見てのお楽しみっ♪」 活弁士は扇子を二度打ち、講釈を続けた。 それは同じ海に生きるもの全てを飲み込もうとした大喰らいの物語だった。小魚と共に海の水まで飲み干し泳げなくなった大喰らいは、海底を割って地の底へ沈んだ。大喰らいは生死の狭間で、地の底の冥界の門を司る影の神官と問答することになる。 漆黒の世界。山のような影の神官が、赤い目を光らせて大喰らいに問う。 「汝はなぜ、それほどまでに喰らうや?」 「我が巨体を保つ為」 「真にそれだけの為と言えようか?」 「他に何がある?」 「汝は、己が愉しみの為に、小さき者、彼らが生きる海すら飲み込んだ。違うか?」 「……知らぬ」 口を閉ざした大喰らいに、黒い靄のように揺らめく影の神官が、静かに宣告した。 「ならば汝、自ら小さき者として海へ帰り、己が身をもって知るがよい」 「それは嫌だ。徒に飲み込まれるだけの者になどなるものか」 「ならば汝、自らの身体の重みをもちて、更に地の底、冥界へと堕ちるがいい」 「それも嫌だ。我はこのまま、再び光りさす海へ帰ることを望まん」 「ならば汝、堕ちることを拒む者を、永久に変わらぬ者として新たなる海へ帰そう」 「それがいい、それがいい。我は再び海の主として、小さき者共を喰らおうぞ」 「……」 口を閉ざした神官は、無数の小さな影へ散り、黒い世界の果てへと消えた。 |
||||
|
そうしては大喰らい再び地上の海へ戻った。しかし、海王はもはや命ある者ではなかった。生きることのない彼に喰われた海の者達が死ぬことはなかった。飲み込まれた彼らは、大喰らいの腹の中で暴れつつけ主を苦しめた。
『あまりの苦痛に大喰らいは七転八倒。海は日々激しく波打ち、暗雲たれ込む曇天の空は稲光り、風もめったやたらに吹き荒れた。そうして、夕霧海は誰も近づけぬ海となり果てた』 活弁士の言葉に合わせ、黒衣の絵師が次々と紙を抜き取る。額縁の中の海は、激しく荒れ続けた。単調で退屈な沼の暮らししか知らなかった沼の主はいつしか、言葉もなくその芝居に見入っていた。たたみかけるような語りに一呼吸おいたユト。身動き一つしなくなった主の様子に彼女は、声なき笑みを浮かべた。活弁士はゆっくり物語の続きを語り始めた。 荒れ続ける海に困り果てた島々の人々は、始まりの島の魔法使いに海を鎮めるよう頼んだ。彼らの頼みに応え、一人の魔法使いが小舟で夕霧海を訪れた。そこで主の苦しみを長い耳で聞きとめた魔法使いは、元凶を突き止めようと、自ら大喰らいの腹の中へ入っていった。大喰らいの腹の中で、彼は外へ出たがる海の者達の頼みも聞き入れることにした。魔法使いは激しく揺れる腹の中から、静かに海王に問うた。 「島々の人々はこの夕霧海を鎮めて欲しいと願い、腹の中の海の者達はここから出たいと願い、あなたは苦しみから逃れたいと願った。私はこの三つの願い全てを叶えようと考えています。しかしそうすると、あなたはもう、今のままのあなたではなくなります。それでもいいでしょうか?」 苦痛に耐えかねた海王はすぐさま返事した。 「それでいい、それでいい。長き耳の魔法使いよ。この苦しさから今すぐ、我を解き放て!!」 「……」 口を閉ざした魔法使いは、声を出さず皮肉な笑いを浮かべた。目を閉じ杖を掲げた彼は、太古の呪い言葉を唱えた。こうして魔法使いは、大喰らいを夕霧海の雫に変えた。腹の中から解き放たれた小さき者達は、魔法使いに礼を述べ、海原へ散っていった。島々の人々は、小舟に乗って何事もなかったように帰ってきた魔法使いを大喜びで迎えた。自分の体が無数の雫に変えられたことに気づいた大喰らいだけが、永久に変わらぬ不満を抱えることになった。平穏を取り戻した夕霧海の波のまにまには、かつてその海の主だった者の呻きが、今も聞こえるという。 「くだらん! 実にくだらんっ!!」 空気を激しく震わせ沼の主が怒鳴り、旅人達を鷲掴みにしようと両爪を広げた。その怒声を制するかの如く、扇子を一打ちしたユトが尋ねた。 「へー。で、うちら喰うんかぁー?」 活弁士は大仰な素振りで泥まみれのターバンを取り去った。豊かに広がる紅の髪から、長い耳が真横に飛び出した。沼の主が息をのむ。長い爪から草むらに滴る泥の音だけが沼に響いた。意地の悪い笑みを浮かべ、ユトが泥沼の主を見上げた。手持ちぶたさに扇子の端で講釈台を打ったり、視線を逸らせて口笛を吹いたり、長耳をわざと動かしてみたり。彼女は余裕の笑みを浮かべ、相手の出方を伺った。やがて沼の主が口を開いた。 「お前は……人ではないのか!?」 ユトが流暢に答えた。 「さっきも言うたやろ、杜人やって。杜人は始まりの島の魔法使い。やたら長生きで根に持つ連中。呪いなんかお手のもんや。繰人も身体を乗り換え何千年も生き続けるしつこい奴等。バラバラにされても平気な連中や。復讐なんて、気が向いた途端いつでもしにくるで。あんた、流神(るしん)の欠片かなんか知らんけど、もしうちら喰うたら、まぁーまともな成仏できんやろな」 「流神だと?」 「知らんかったら気にしな。とりあえず腹ん中ズタズタにされるのは間違いないで。な、バムッ♪」 早くも芝居道具を片づけていた絵師が、相方の呼びかけに応え、俯いたまま六本の腕を突き出した。蜘蛛のように広げられた腕の先の六つの手には、古今東西大小様々な剣が握られていた。沼の主が一瞬、怯えたように身をのけぞらせた。物騒な業物は、次の瞬間には黒衣に納められていた。バムザは何事もなかったように、片づけを続けた。沼の主はやがて、悔しげに低く呻き始めた。 「…うぬー」 「で? どないなん?」 ユトが、にやにや笑いながら答えをせかした。沼の主が渋々大声を張り上げた。 「…去れい! 今すぐ何処へなりと行くがよい」 「あー、やだねぇ。勝負に負けてまでいばり散らす奴って。それよりあんた、覚悟はええんやろな」 二人に背を向け沼底に戻ろうとしていた主を、ユトが呼び止めた。 「何のことだ?」 背を向けたまま、主が問うた。 「決まってるやん。勝負に負けたあんたには、誓いでも立ててもらわな。うちらの気ぃ、収まらんわ」 「誓いだと?」 「そや。あんたみたいな化けモンが威張ってるから、困った旅人に対する持てなしもないんや。うちらもかなり迷惑したからなー。『三百年、沼から出てくんな』、誓いはこれで決まりや」 「なんだと! お前達を喰わなかっただけで、なぜそんな約束までせねばならんのだっ! ふざけるなっ!」 振り返った主が大声を張り上げた。バムザの片手が閃くと、その口の中に一枚の札が投げ込まれた。 「んぐっ! 何を入れたっ!!」 「呪い言葉で書かれた誓約書。馬鹿はすぐ忘れるからな。体に覚え込ませとくわ。えーか、三百年やで。三百年経たずに沼から出たらあんた、腹ん中から木っ端微塵や。その紙から吹き出る黒い火、めちゃめちゃ熱い上にちょっとやそっとじゃ消えんからな。よう覚えとき」 不適な笑いを浮かべ、ユトが一睨みする。自分の脅しも話も通じる相手ではない、そう確信したのだろう。沼の主は、呻きながら沼底へ沈んでいった。 「しかしほんま、主にしては見かけだけの気の小さい奴やったなぁ。ありゃ多分、さっき沼の縁におったガキ共がこしらえた泥ダルマに、空から降ってきた爪の垢ほどの流神の欠片が混じって出来たんやで」 片づけを終え躰を起こしたバムザが、一枚の紙を見せた。 『即席の芝居で脅され、嘘の誓約書で騙され、少し可哀想』 「よーゆーわ。あんたも自慢げに<鉄杜>から物騒なもん出しとったやん。あの小言だらけの長老にバレたら大目玉や。うちはもっと穏便に、この耳見せただけやん。……ギンガン、ちゃんと伝えときや」 ユトの最後の一言に、銀色にくすむ彼女の耳飾りが微かな音を立てて震えた。長い耳を横目に髪をかき上げると、ユトは泥まみれのターバンを巻き付けた。が、すぐさま気持ち悪さに顔をしかめた。 「う゛……とにかく村行って、ひとっ風呂浴びよ」 |
||||
|
|||||||||